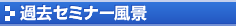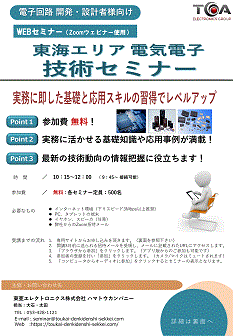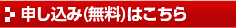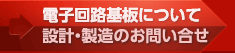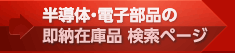個人向けとは異なり、業務用途ではまだまだWinowos7が多く使われています。しかし、本年11月以後はWindows7がインストールされたパソコンの出荷がほぼ終了するため、どうしても11月以降もWindows7の購入が必要な場合は、組込用として販売が継続されているEmbedded版を入手せざるをえません。Embedded版は、組込用途以外に流用する際のハードルが高いため、もはやWindows10への移行は必須と言える状況です。
■Windows7/8.1からWindows10へ
Windows10は新種や未知のウイルスに対する耐性が強い上、市販ソフトと遜色の無いアンチウィルスソフトを標準装備するなど、Windows7とは比較にならないくらいセキュリティ面の充実化が図られています。しかし、セキュリティ対策が充実化される一方、これまで使用者側の管理権限下で任意にコントロール可能だったアップデートが、Windows10からはOS側の管理となり、アップデート実行に関わる決定権は使用者側には無くなりました。結果として、インターネットに接続されている限りアップデートが自動で実行される仕様になったのです。
■年2回実施のメジャーアップグレード
ここで最も問題になるのは、Windows3.0→8.1と、進化を兼ねて行われていたメジャーアップグレードに匹敵する「機能更新」です。Windows10以後はアップデートの中でこの機能更新が行われるのです。機能更新は年2回実施され、インターネットを通じて3GB近いファイルのダウンロードとインストールが実行されます。ほぼOSの入替えに匹敵しますので、機能更新のインストールが実行されている最中はパソコンは利用できません。CPUのスペックが最も高いパソコンでも40分を要し、低スペックなCPUのパソコンの場合だと半日を費やしてしまいます。これに対しては有効な対策の用意が無く、OSの設定でアップデートを実行させたくない時間帯の指定は可能であるものの、実行を開始する時間の指定が出来ません。そのため、業務時間内に機能更新が掛かってしまい業務が中断してしまうなど現場の生産性を落とすトラブルの原因になっています。
■アップデートの問題点
問題点はこれに留まりません。Windows7や8.1からWindows10にグレードアップして使用してる古いパソコンの場合、パソコンが機能更新に追従できずにアップデート前への復元と機能更新の実行がループしたり、これまで稼動していた周辺機器が機能更新の後に非適合となってしまうなどの問題も発生しています。このように機能更新も含めて一切のアップデートが任意にコントロール出来ない事がWindows10の抱える問題点と言えます。特に無人の設備や人の手が掛からない場所に設置したパソコンにトラブルが発生した場合、停止してしまいます。
■問題点に対する対処策
アップデートに関わるトラブルが発生すると、解決手段を持たないパソコン使用者は情報システム担当者(無ければ総務部門)から救援要請が寄せられる事となるのですが、Windows10機を多数抱えた場合、アップデート後に発生したトラブルの対処に追われてしまいます。結果的に対策の部署や専任担当が必要となってしまうのです。このようなアップデートの管理に関わる問題に対処方法として2つの手段が講じられています。
【1】Windows10アップデートの能動的管理
Windows10の全ての更新ファイルを収納する専用サーバーをネットワーク内に設置し、この専用サーバーを介してネットワーク配下のパソコンにアップデートを実行させるという方式が有ります。パソコン側にはデフォルトのアップデートを停止させて専用サーバーからのみアップデートを実行するソフトウェアをインストールします。アップデートはアップデートの管理者の権限でコントロールを行い、パソコンのメーカー・機種別により更新ファイルのキッティングや、グループ別にアップデート実行日を変更するなど、能動的な管理が可能となります。既に1000台以上のWindows10パソコンを抱える企業で導入が進んでおり、アップデート管理の効率アップに役立っています。
【2】Windows10の機能更新の完全停止
こちらは【1】とは逆に、機能更新が適用されないLTSB版OSのWindows10を採用する手段です。LTSB版は組込用であるため、既に医療機器や工作機械の他、デジタルサイネージ等の無人設備等、一般版OSとは異なる用途に採用されています。Embedded版は、インターネットに接続していてもセキュリティとバグフィックスのアップデートは実施されますが、機能更新は実施されません。機能更新が停止されるメリットは多いのですが、OS単体でのパッケージ販売が行われていない上、10本以上でライセンス契約をする必要が有ります。LTSB版は、仮にライセンスで購入したとしても単価が一般版と比較して割高な上、OS入れ替えの手間も掛かる事から、導入のハードルが高い事が難点です。 なお、マイクロソフト社とOSの取扱い契約を交わしているメーカーからであれば、1台単位でLTSB版がインストールされたパソコン(産業用PCや業務用タブレット等)が購入可能です。
弊社ではアップデートの管理および、LTSB版OSがインストール済みのパソコン導入のご相談を受け賜っております。お気軽にご相談下さい。
小型、中型、大型ドローンが活躍することがビニネスになっている情報がテレビ、ネットで多く取り上げられております。
ドローンの市場規模が現在約400億円で5年後には4倍の規模に成長するようですが、身近の情報では各産業分野でドローンを取り入れる計画し試験運用経て運用になりつつあるようで、性能も数年前とは格段に上がり素材、制御、セキュリティ、安全面、持続性、性格、他もそれぞれ高機能、低価格、高品質になってきていると思います。ドローンの導入で何ができそうか?できなかったことができるようになるのか?私なりに考えてみました。
〇農業分野
私の実家は少さな農家をしており両親も年老いて体も思うように動かず、農業機械操作、農薬/肥料散布、草刈り、他と手間と労力がかかる仕事です。ドローンが替わってできそうな仕事はすでに実績もあると思いますが、農薬・肥料空中散布散布を面積により簡単設定で自動補給もできればいいなと思います。草刈りも大変な作業で山間地のため斜面が多くその草刈りをしてもらえたら助かります。またドローンで鳥獣被害対策ができればセンサー等を駆使し夜間でも自動走行し監視、威嚇等(動物が嫌う:光、超音波、におい等)ができればいいなと考えます。
弊社では、測定機器メーカーから依頼を受けまして、地面に埋め込まれたセンサから無線で地上でデータを拾う為のセンサ基板の開発を行いました。 特定小電力の無線開発が特徴です。 設計当初は、0.5uVの信号を処理する為に低ノイズ対応に苦慮したり、半導体精度の違いにより特性がでなかったりと大変な部分がありましたが、 最終的には、お客様の満足いく特性が出る製品を開発することが出来ました。 元々は、寿命も短く、製品交換が定期的に必要でありましたが、弊社にて開発をさせて頂きました製品は、低消費電力のため、製品の交換作業の工数を削減でき、お客様に喜ばれる製品を開発することができました。こちらのお客様については、現在も定期的に開発のお仕事を頂き、お客様の競争力アップに貢献をしております。弊社、測定機器の開発も得意としておりますので、お困り事項ございましたら、お気軽に、東亜エレクトロニクス株式会社までお問い合わせをお願い致します。
連日の猛暑日に比べてかなり涼しくなり、秋が近づいてきている事が実感出来るようになってきました。朝晩は寒いと感じることがありますので体調管理には十分注意を払うようにして下さい。
ここ最近ではアメリカが中国に対して追加関税をかけることが決定し、景気に影響が出ることが懸念されております。日本は好業績の企業が多い中で、中国での生産見直しも検討しているようです。中国内需や輸出に影響が出るようであれば、世界的に景気が悪くなる可能性もあり不安になります。
その中では自動車のEV化や自動運転化などは活況であり、その中心となっているのがモータと電池であります。
世界の電力の半分はモータの電力と言われておりますが、ますます需要は高まっていきます。
モータを少ない電力で効率よく回す技術として各半導体メーカーがしのぎを削っておりますが、弊社が取り扱っている東芝でもモータ制御ICやベクトルエンジンを搭載したマイコンに注力しており、今後ラインナップが増えてきます。
6月に東芝モータ制御の基礎技術という技術セミナーを開催しましたが、来年度もモータ関係のセミナーを開催する予定です。
来年度の技術セミナーにもご期待ください!!
M社の積層セラミックコンデンサの量産0603サイズ(0.6×0.3×0.3mm)と極小な部品に切り替えていく方向が話題になっておりますが単なるサイズ変更と思いきや耐圧も低くなりラインナップも少なくなり回路設計をするにも高耐圧回路に使用できる積層セラミックコンデンサも全く無くなるのではないのですが積層セラミックコンデンサを使用しなくても機能満足できる設計が必要になるのではと考えます。(又他コンデンサで代用も検討が必要)
又、ケースサイズ0603タイプ(0.6×0.3×0.3mm)が主流になっていくことは製造ノウハウも必要になってくるようで厚みも0.3mmなので実装する際の少量クリーム半田で実装し又メタルマスクも薄くする必要がありそうで従来の他面実装部品と半田付条件との関係も考慮すると部品実装パターンの設計、メタルマスクの設計、部品実装条件を見直す検討が必要となってきます。今後新規で設計する際も新たな設計ノウハウが必要となってきますが現行基板をどのように部品変更し機能変えず、品質も保ち製品を製作するリスクが増えることを対処することが課題となっており日々奮闘しております。



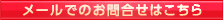

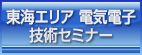
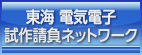
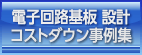
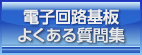
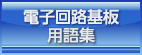
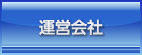
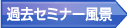




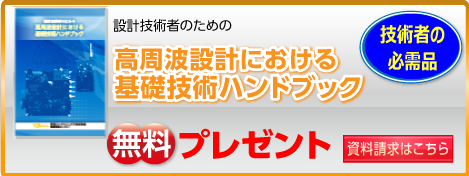
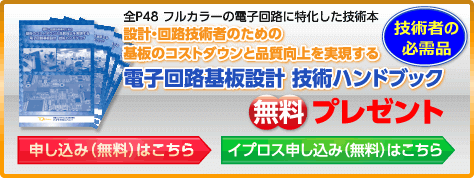

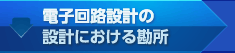
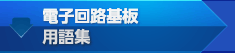

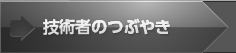

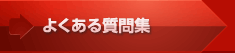
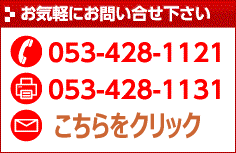
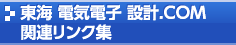

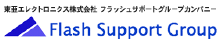
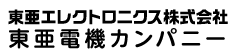



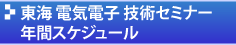
 第91回2025年9月18日(木)
第91回2025年9月18日(木)